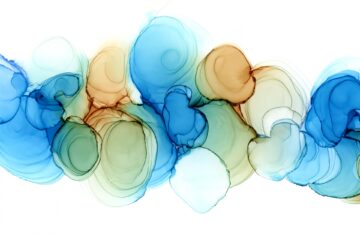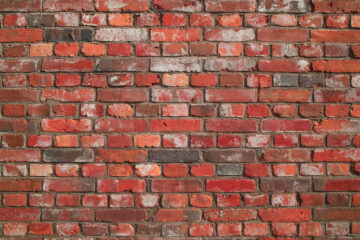ユルゲン・クロップ監督が就任してリヴァプールFCは復活した。18-19シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグを制覇している。毎試合、ゲーゲンプレス戦術をベースに息つく間もなく仕掛け続けるパッショナブルなサッカーが繰り広げられる。相手にとっては脅威、観客にすればなんとも魅力的なこのスタイルが世界を席巻している。
一見結びつきそうもない「多様性社会」、国土交通省が掲げるこの先の社会の在り方である。まずは序文をみてみよう。
2030年の日本の社会におけるキーワードは、多様性(ダイバーシティー)。人種・性別・年齢などに一切関係なく、すべての人々が自分の能力を活かしていきいきと働ける社会が実現している。外国人にとっても魅力的に変わった日本の社会には、アジアを中心に海外からの留学生、就労者が増え、人口の20%は外国人が占めるまでになっている。こうした多様性にあふれる社会の中で、日本人は自分たちの文化や独自性を再発見し、自らのアイデンティティを明確にし、魅力ある国を再び作ることに成功している。またこの社会は、一人ひとりの生活を重視する社会でもあり、労働スタイルが効率的になることで、8時間勤務が実現し、自然のリズムにしたがい、自然の流れと共生する、資源循環型社会でもある。多様な価値観の人々がお互いに相手の文化や考えを尊重する中で、世界の平和、貧困の撲滅にむかって貢献する日本の能力も醸成されている。
単一民族国家であったことが一因だろうが、日本では多様性の許容範囲が狭く、皆で足並みを揃えることが美徳とされてきた。しかし、世界でみれば日本は196か国のうちのひとつでしかなく、地球規模でみれば人間は数多ある生命体のうちのひとつでしかない。みんな違くて、みんないい。違う前提で物事を捉えた方が自然なのだ。短所は程々に長所を思いっきし伸ばす。変化を恐れずトライ&エラーで創っていく。超訳すると多様性社会とはこんなイメージである。
2020年1月に南野拓実選手がリヴァプールFCに移籍し、その5日後にFAカップで先発デビューを飾った。なぜ、メッシでもC.ロナウドでもない彼が、世界一のクラブに移籍でき、即スタメンで試合に出場することができたのか。多様性社会の序文に結びつけながら考えてみたい。
自らのアイデンティティを明確にする
私は多様性社会で一番の肝は個人力だと思っている。自分の特性を見極め、弱点よりも「強み」や「好き」を極限まで伸ばす。偏りをよしとしよう。全員がオールマイティな能力を有する必要はなく、足りない部分は補い合えばいいのだ。
南野は体格が大きくない。プレミアリーグではフィジカルで苦戦するだろう。それでも似た体型のダビド・シルバはマンCで成功し続けている。それは彼が激しい肉弾戦は他に任せ、フィニッシュに絡むクリエイティブのみに専念しているからである。サッカーではピッチ上の特異な選手たちが適材適所されることで化学反応が起こり人数以上の力が発揮される。南野は特徴であるゴールへの意欲、反転力、相手の嫌な隙間に身を置き続ける嗅覚、走力と気力を磨き続けるべきである。割り切って特化することで更なる成長が待っている。
お互いに相手を尊重する
相互尊重の関係に成るには、3つの段階が必要だと思っている。自分で自分自身を認めること、相手を認めること、相手から認められることだ。その中で、手っ取り早く相手から認めてもらうひとつの方法は、結果を出すことである。たとえ納得がいかない環境に居たとしても、そこで結果を出す。結果がなければ何を言っても遠吠えにしかならない。結果がひとつの根拠となり、自分は何ができる人なのか、周囲にどんな恩恵をもたらせる人なのかを、初めて証明することができる。
しかしながら、ここに大きな落し穴がある。「石の上にも三年」のことわざは正しい。そう、結果は一朝一夕には出ないのだ。
南野はザルツブルグで結果を出した。移籍当初から順風満帆だったわけではない。事実、彼は4年間も在籍した。ブレイク前の若いタレントを集め、実践を通じて育成させ、ビッグクラブへの売却をウリにするチームにおいて、売れ残りと言われても仕方のない年数である。彼は腐らなかった。メンバーが年々入れ替わるこのクラブで、自分がやれることに集中した。英語とドイツ語を学び、言葉とプレーで仲間との相互理解を深めて、ゴールという結果を出し続け、チームをリーグ連覇させ、彼自身のステップアップの機会へ近づいていった。
自分の能力を活かせる社会
多様性社会では個性の違う人材の適材適所が重要になる。ヴィジョンが必要だ。パズルでいうところの、異形なピースの組み合わせに必要な一枚の絵である。サッカーにおける選手とチームの関係にも同じことがいえる。
ユルゲン・クロップにはサッカー哲学があり、それは長年に渡って構築されたクラブのDNAと似ている。今のリヴァプールには一枚岩の印象がある。南野がCL予選リヴァプール戦で魅せた活躍に、選手、スタッフ、監督、観客全員が「なんてリヴァプールらしい選手なんだ」と共感を覚えた。「リヴァプールFCとはこういうクラブである」という言葉以上に明確なヴィジョンがあったからこそ生まれた反応だろう。南野はひとりで年間20点とってチームを勝たせるケインやザハやヴァーディのような選手ではない。それでも自分が得意とする部分を磨き続けた結果が見初められ、アンフィールドの一員として迎え入れられることになったのだ。
南野のデビュー戦でのパフォーマンスは悪くも良くもなかった。デーリーメール紙は「6点(10点中)インパクトを残すには苦戦した」と、チーム最低の評価を下した。しかし私には、70分の交代に満員の観衆がみせたスタンディングオベーションに、今後の彼の活躍が約束されているように感じられた。
サッカーは社会の縮図である。我々がこの先の社会で生き抜くためのヒントが、南野とリヴァプールの関係性の中に埋め込まれている。